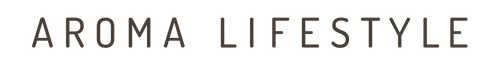植物の香り成分がギュッと凝縮された「アロマオイル(=精油)」。香りを嗅いで楽しむ以外に、お風呂や美容、掃除など、使い方がたくさんあるのが大きな魅力のひとつです。
そこで今回は、初心者の方でも簡単に楽しめる、アロマオイル(精油)の使い方をご紹介します。
 小田ゆき
小田ゆきアロマオイル(精油)を安全に使うために知っておきたい注意点も紹介します。これからアロマテラピーを始めたいという方はぜひ参考にしてくださいね。


小田 ゆき
アロマとメディカルハーブのスペシャリスト
アロマ専門メディア『AROMA LIFESTYLE』主宰。YouTubeでもアロマ情報を発信し、チャンネル登録者は2万人を超える。セミナー講師、コラム監修、メディア出演などで幅広く活動中。自身の経験を踏まえた、わかりやすく丁寧なレッスンに定評がある。プライベートでは1児の母。詳細プロフィールはこちら
芳香浴(ほうこうよく)
「芳香浴(ほうこうよく)」とは、精油の香りを空間に広げて楽しむアロマテラピーの最も基本的な方法です。
手軽に行うことができ、リラックスや気分転換など、心身のバランスを整えるのに役立ちます。
香りを拡散する芳香器には「アロマディフューザー」や「アロマランプ」などさまざまな種類がありますが、専用の道具がなくても大丈夫。
使う場所や目的に合わせて、適した方法を選んでみましょう。
アロマディフューザーで楽しむ


芳香浴の中で最もポピュラーなのが、専用の芳香器「アロマディフューザー」を使って香りを楽しむ方法です。
一番のメリットとしては、空間に精油の香りを効率的に広げることができること。そのため、リビングや寝室など、お部屋でアロマを楽しみたい方におすすめです。
アロマディフューザーには、定番人気の「超音波式」のほか、拡散力に優れた「ネブライザー式(空気圧縮式)」などがあります。
・超音波式ディフューザー
主流のミストタイプは、使うたびに精油や水を入れるなど手間やこまめなお手入れが必要ですが、少量の精油で利用することができるのがメリット。
デザインのバリエーションも豊富で、無印良品など身近な店舗でも入手しやすく、動作音が目立たないので書斎や寝室で使うのにも適しています。本体価格も比較的お手頃で、2,000円台から購入可能。
・ネブライザー式ディフューザー
近年人気が高まっている、水を使わないタイプのアロマディフューザー。
ミストタイプより高価で、多少動作音が気になるなどのデメリットはありますが、スイッチひとつでアロマを手軽に楽しめるシンプルな操作性で、お手入れもラク。拡散力に優れ、10畳を超えるリビングなど広い空間に適しています。
ティッシュやコットンを使って


最も簡単なアロマオイルの使い方です。
精油は揮発性があるため、ティッシュやコットンに垂らしておくだけでも自然に香りが広がります。
特別な道具が必要ないので、寝る前に枕元に置いたり、仕事や育児の合間の気分転換にもおすすめ。旅先のホテルのニオイが気になるときにも役立ちますよ。
部屋全体を香らせることはできませんが、自分だけでちょこっとアロマを楽しみたいときに最適な方法です。
●方法
ティッシュやコットン、ハンカチに精油を1〜2滴垂らし、近くに置いて(精油が家具などに触れないように)香りを楽しみます。
- ハンカチを使う場合はシミになることがあるので、汚れてもよいものを使いましょう。
- 布や木製製品に精油が付着するとシミができる場合があるので、机に置くときには受け皿があると安心です。
アロマストーン


ティッシュやコットンでは味気ない…という方には「アロマストーン」を使うのもおすすめです。
アロマストーンとは、素焼きの石や石膏で作られたもの。精油を垂らすだけで簡単に使え、ちょっとしたインテリアとしても楽しめます。
自然に香りが広がるものなので、電気式のアロマディフューザーに比べると香りの拡散力は弱いですが、読書やリラックスタイムに自分ひとりで香りを楽しみたいときや、玄関、トイレ、デスク、車など、狭い空間の芳香にも適しています。
アロマストーンは無印良品やアロマ専門店、ネット通販などで購入することができます。素材が石ではなく木製の「アロマウッド」と呼ばれるアイテムも人気です。


アロマライト、アロマポット
電気やキャンドルの熱で精油を温めて拡散させるディフューザーです。穏やかな香りと柔らかい光で、癒し効果が得られるのが魅力で、夜のリラックスタイムにも最適です。
熱を使うので、香りが変質しやすい柑橘や針葉樹の精油よりも、樹脂(フランキンセンス、ミルラなど)や樹木(シダーウッド、サンダルウッドなど)などベースノート寄りの精油の芳香に使うのがおすすめです。また、小さな子供やペットがいる家庭では、火を使わない「アロマライト」が安心です。


吸入
「吸入」は、精油の芳香成分を鼻や口から積極的に取り入れる方法です。
鼻や喉に直接作用させることができ、鼻づまりや喉の痛みなど風邪のひき始めに効果的な使い方です。
ティッシュに垂らして乾式吸入を行うほか、スチームとの相乗効果が期待できる「蒸気吸入」がポピュラーです。
マグカップで蒸気吸入


蒸気吸入は、立ち上る蒸気とともに精油の芳香成分を吸い込む方法で、とくに乾燥しがちな冬に試したい取り入れ方です。
<蒸気吸入の方法>
- マグカップに40〜80度程度※のお湯を入れる。※お湯の温度が高すぎると、精油成分がすぐ揮発してしまうため。沸かした湯に少し水を加えると◎
- 精油を1〜3滴垂らす。
- 目を閉じてから蒸気に顔を近づけ、深呼吸するようにゆっくりと蒸気を吸い込む。そのまま蒸気が出なくなるまで5分ほど行う。※頭からバスタオルをかぶり、蒸気を逃げないようにするとさらに効果的。
- 精油成分が目の粘膜を刺激することがあるため、必ず目を閉じて行います。
- 咳が出るときや喘息の人、小さな子供には避けましょう。
- マグカップのお湯を間違って飲まないようにしてください。
マスクで


マスクに香りを染み込ませて吸入する方法も。肌に触れない外側に、精油を1滴垂らします。
香りが強いとむせてしまう場合があるので、マスクをつける5〜10分前に精油を垂らし、香りをなじませておくのがおすすめです。
精油の原液が肌に触れると刺激が強すぎるため、精油のついた部分が直接肌につかないように注意してください。初心者の方はあらかじめアロマスプレーを作って、それをマスクに吹きかける方法がより安全です。
アロマバス(沐浴)


「アロマバス」は、精油の香りとともに入浴する方法のこと。
香りを楽しむだけでなく、皮膚からも精油成分が吸収されるため、芳香浴よりも高い効果が期待できます。
また、入浴による温浴効果やリラクゼーション効果も加わり、アロマとの相乗効果も得られるのがポイントです。
精油はお湯(水)に溶けないため、浴槽にそのまま垂らすと原液が肌に触れて、赤みや刺激などの肌トラブルを招く恐れがあります。そのため、あからじめ精油を植物油 or 専用のバスベース(乳化剤)に混ぜてから浴槽に入れるのが大切なポイントです。
アロマバスで注意が必要なアロマオイル(精油)など、詳しくは以下記事をご参照ください。
全身浴・半身浴
肩までつかる「全身浴」は、効率的に全身を温めることができるため、疲労回復におすすめです。「半身浴」は身体への負担が少なく、長時間お湯につかることができるので、読書などリラックスした時間を過ごしたいときに適しています。
<全身浴・半身浴の方法>
植物油小さじ1程度 or 規定量の乳化剤に精油を1〜5滴(半身浴は1〜3滴)混ぜ、浴槽のお湯に入れてよくかき混ぜてから入浴します。
- リラックスしたいときは38〜40度のぬるめのお湯で長めに、リフレッシュしたいときは42度程度の集めのお湯で短時間入浴を。
- バスソルトを使えば、保温作用や発汗作用がアップします。アロマバスソルトの作り方はこちら。
部分浴(手浴・足浴)
「部分浴」は、身体の一部だけをお湯につける方法です。服を脱がずに手軽に楽しめるので、気分転換したいときや、病気やケガでお風呂に入れないときにもおすすめです。
《手浴(しゅよく)》
準備がラクで、手軽にできるのが魅力。頭痛など首より上の不調に役立ちます。
《足浴(そくよく)》
全身の血流改善に役立ち、冷えや生理痛、足のむくみが気になるときに。くるぶしまでつけると効果的。
<部分浴の方法>
洗面器にやや熱めのお湯を張り、植物油小さじ1程度 or 規定量の乳化剤に精油を1〜3滴混ぜたものを加え、よくかき混ぜてから手や足を浸けます。
アロマシャワー
手軽に楽しめる「アロマシャワー」。バスルームの床に精油を1〜3滴垂らしてからシャワーを浴びます。
朝のシャワータイムには、元気が出るオレンジ・スイートや、眠気を吹き飛ばすペパーミントを。旅先で湯船につかれないときにも最適です。
※精油が直接肌に触れないように注意してください。また、床の材質によってはシミなどになる場合があります。あらかじめ目立たない場所で試してから行うのが安心です。
アロママッサージ(アロマトリートメント)


「アロママッサージ(アロマトリートメント)」は、精油の香りとマッサージの相乗効果で深いリラックスをもたらすだけでなく、美肌に整える、血行や老廃物の排出を促す、筋肉のコリを和らげるなど、心身への高い効果が期待できます。
マッサージオイルの作り方も簡単で、精油を植物油(キャリアオイル)に混ぜ合わせるだけで手軽にチャレンジできます。
アロママッサージの方法
精油の原液は刺激が強いので、直接肌につけることができません。
ホホバオイルやスイートアーモンドオイルなどの植物油(キャリアオイル)で低濃度に薄めてから使います。
精油を薄める割合は1%以下が目安ですが、使う精油の種類や使用方法、使う人の健康状態などにより多少変わってきます。
とくに顔などのデリケートな部分に使う場合や敏感肌の人は、さらに薄めの濃度(0.5%以下)を心がけましょう。
| 植物油の量 | 10ml | 20ml | 30ml | 40ml | 50ml |
| 1%濃度 | 2滴 | 4滴 | 6滴 | 8滴 | 10滴 |
| 0.5%濃度 | 1滴 | 2滴 | 3滴 | 4滴 | 5滴 |
- 精油や植物油は高品質なものを選びましょう。
- 敏感肌の人は0.5%以下の濃度で行い、必ずパッチテストをしてから行ってください。
- かゆみや炎症などのトラブルが発生した場合は植物油を含ませたコットンや綿棒で拭き取り、石けんで洗い流し、必要に応じて医療機関を受診してください。
フェイシャルスチーム
「フェイシャルスチーム」は、精油成分を含んだ蒸気を顔にあてる方法です。
蒸気の温熱による血行促進や保湿効果も期待でき、肌荒れやくすみ、ニキビなど肌トラブルの予防・軽減に役立ちます。
フェイシャルスチームの方法
洗面器に熱めのお湯を入れ、精油を1〜3滴垂らします。
目を閉じて、10分ほど蒸気を顔に当てます。肌が敏感な人は5分間を目安に。
蒸気が逃げないよう頭からバスタオルをかぶって行うと効果的。
精油成分が目の粘膜を刺激することがあるため、必ず目を閉じて行います。
湿布
「湿布」は、精油を含ませたタオルを体にあてる方法で、主に痛みや筋肉のコリを感じるときに用いられます。
一般的に、慢性の肩こりや腰痛、生理痛には、体を温めて血行を促す「温湿布」が。ねんざや打撲の直後など急性のトラブルやスポーツ後のクールダウンには「冷湿布」が効果的とされています。
湿布の方法
洗面器にお湯(または冷水)をはり、精油を1〜3滴落とします。
タオルで水面に浮いた精油をすくい取るようにし、精油が肌につかないように注意して絞ります。
精油がついた面が内側になるように折りたたみ、気になる部位にあてます。
- 精油のついた部分が直接肌につかないように注意します。
- 目のまわりや皮膚の薄い部分への使用は避けてください。
手作りコスメ・アロマクラフト


精油は手作りコスメやアロマクラフトに活用するのも人気です。化粧水やクリーム、入浴剤、虫除けスプレーなど、用途に合わせて自分好みにアレンジできるのが魅力。少しのコツさえおさえれば、誰でも簡単に作ることができます。
アロマ化粧水(ローション)
化粧水は最も手軽な手作りコスメのひとつ。自分の肌質や肌悩みにあった精油で化粧水を作ってみましょう。


アロマクリーム
保湿ケアに欠かせないクリームづくりも、実は少ない材料で手作りすることができます。一番簡単なのは、シアバターに精油を混ぜるだけ。
虫除けアロマスプレー
夏のおでかけの必需品、虫除けスプレーも手作りなら安心です。
レモングラスやゼラニウムなど虫が嫌がるアロマを使うのがポイント。汗のニオイ対策などにも使えて万能です。


- 精油や基材は高品質なものを選びましょう。
- 光毒性のある精油の使用は十分注意してください。(ベルガモット、レモン、グレープフルーツなど)
- 使用前には必ずパッチテストを行い、かゆみや赤みなど肌トラブルがあれば使用を中止してください。
- 保存料を使わない手作り化粧品は劣化しやすいため、高温多湿を避け、冷暗所(夏場は冷蔵庫)に保管し、早めに使い切ります。
- 自分で作った手作りコスメの使用はすべて自己責任です。
掃除・ハウスキーピング
精油の中には、抗菌作用や消臭作用をもつものがたくさんあり、掃除にも活躍します。
心地よい香りに包まれて、お掃除タイムも楽しく!
キッチンやゴミ箱、玄関の気になるニオイや、お風呂のカビ対策など、多彩な使い方ができます。


掃除用スプレー


掃除用スプレーを1本手作りしておけば、拭き掃除や消臭などマルチに使うことができます。
キッチンの汚れにはオレンジ・スイート、カビにはティーツリーの精油がおすすめ。
作り方は以下記事でご紹介しています。


消臭剤(アロマ重曹)
消臭力のある重曹に精油を混ぜれば、からだにも環境にも優しい天然の消臭剤に。
清潔なジャム瓶など口の広い容器に重曹を100g入れ、精油を10滴加えてよく混ぜます。靴箱やトイレなどニオイが気になる場所に置いたり、ゴミ箱に直接ふりかけてもOK。
シンクなどの汚れ落とし(クレンザー)としても活躍しますよ。


掃除機のにおい取りに


気になる掃除機のニオイもアロマで解決。
小さくちぎったティッシュに精油を1〜2滴垂らし、掃除機で吸い込んでからいつも通り掃除機がけをするだけと簡単。
消臭作用のあるレモンやペパーミントの精油を使えば、掃除機の排気も爽やかに。


アロマの使い方の幅を広げて、潤いのある暮らしを
さて、今回はアロマオイル(精油)の使い方にフォーカスして、さまざまな利用法をご紹介しましたが、参考になりましたでしょうか?
初心者の方は、まずは精油1本から始められる「芳香浴」がおすすめです。
少し慣れてきたら、アロマバスやアロママッサージ、スプレー作りのようなアロマクラフトにも挑戦してみましょう。アロマの効果をより実感できるはずですよ♪



アロマオイル(精油)はたくさんの使い方ができるのが魅力です。まずはみなさんの生活に取り入れやすい方法から試してみてくださいね^^
\ 注目のレッスン&イベント情報 /
YouTubeチャンネルメンバーシップ『小田ゆきの癒しのアトリエ』NEW!
月2回のライブ配信を中心に、通常の動画では触れられないアロマのより深い知識やセルフケアの方法をお届け。
- メディカルアロマテラピーに興味がある
- 忙しい日常の中で、自分のための時間をもちたい
- 小田ゆきの生き方や考え方、アロマ活動が気になる
このような方に喜んでいただける特別なライブセッション&特典を、毎月1,790円でお楽しみいただけます。詳しくは「小田ゆきのYouTubeメンバーシップ」で、今すぐチェック✨
ビギナーさん向け、暮らしに役立つアロマ入門講座(録画配信)を好評開講中♪
- いつもの◯◯にプラスするだけの活用法
- 森のリードディフューザーづくり
- 肌も心も整う、保湿アロマバームづくり
などなど、知っておきたいアロマの基本から、日常生活に役立つ活用レシピを全6回で学べるレッスンです。
ほか、著名な先生による1,500以上の講座が月々1,980円〜受講し放題! 詳細は「miroom(ミルーム)」にてチェック♪
その他、最新のレッスン情報はInstagram(@aroma_lifestyle)などでお知らせします🌼